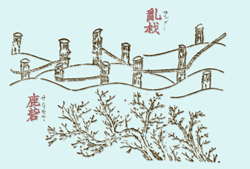 乱杭・逆茂木 乱杭・逆茂木
About the protectons in the age of Civil Wars.
戦国時代というのは社会秩序が乱れ、文字どおり日本列島の各地で戦いが行われていた時代だったのは皆さんもご存知の通りです。当時の技術や知恵を総動員して生活し、戦いにおいてもそれは同じでした。着るものから建物、システムに至まで、よく見ると、とても興味深い事が見えてきます。ただ満たすための道具が発達していなかっただけで、今でも通用するソフト的なもの(発想や考え)は凄く興味あるものが沢山あります。
私も歴史は好きなのですが、特にそういう隠れた時代の一面というものにも大変興味があります。戦国時代というのは、今ではとかくイメージ的に捉えられがちですが、やはり生活するには今の方がずっといいと思いますね。
さて、今回は「乱杭・逆茂木」という、戦になった時に良く使われる道具というか方法なのですが、戦国時代を取上げた古文書の中にはこの「乱杭・逆茂木」という言葉はよくでてきます。また、この方法は古くから行われていたようで「建内記」という古文書の中に1441年(嘉吉元)7月26日の条項として登場しています。
「乱杭・逆茂木」とはどんなものかというのは、イラストをご覧頂ければある程度わかると思いますが、「逆茂木」は適当な木を切って、枝の方を敵に向けて一面に並べます。その木はなるべく堅いものを選び、枝を鹿の角のように鋭く削ったものです。一方、「乱杭」は、杭を沢山地中に埋めて、その地面から出たところの端々をナワで結んで障害物としたものです。
双方とも今で言う進路妨害のためのバリケードですが、「逆茂木」はどちらかというと陣地の構築したまわりに設置し、「乱杭」は水辺などに設置して、足をすくうなどのために用いられていたようです。まあ、バリケードですので、いざ戦いとなれば、何でも、どこでもという感じだったと思います。
ちなみに「武用弁略」という古文書には、攻防用具について「要害ノ六具ト云ウハ乱杭・鹿砦(さかもぎ)・菱・勢楼・竹束・楽堂等也。(中略)鹿砦ハ棘木(いばらぎ)ナリ。故ニ鹿角砦(ろっかくさい)ト云」とありその説明がされています。他に落とし穴や柵も用途により様々なものがあったようです。
当然、戦国時代を生きた摂津池田家でもこのような心得はあったと思われますし、実際使われたと思います。中世の名残りを強く残すと思われる池田城は、日本の城を代表する姫路城や名古屋城といった近世の城とは違い、こういった自然の地形やものを利用する城だったのですから。
池田城に関する発掘調査書などでは、このような記述は出てきませんし、中世の城自体、関心もあまり注がれないことからこの先も明らかにされる事はないでしょう。
摂津では、名だたる国人に成長した池田家は、京都の中央政権との結びつきを強める中で、城の防御面においても割合、先進的だったのだろうとも思います。また、経済的にも余裕があったようですし。
一方で、城郭史的な観点から見ると、池田城は中世から近世へ移る途中で、完成されたスタイルもなく、つかみ所のない城なのかもしれません。しかし、規模的には、大阪府内でも5番目の規模(うっかり出展を忘れてしまいました)の城だそうです。これは、分かっているだけの部分で推定してこの規模ですから、縄張り的(勢力圏)には、かなり大きなものがあったのではないでしょうか?
ですから、その末端の砦や館などは、このような防御策を採っていたのではないかと思います。当然、池田城は文献上でも、発掘結果でも、幾度となく落城した事が知られていますから、時には池田城の周りにこのような防御策を講じていたのではないでしょうか?
|